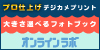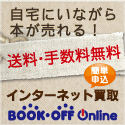料理とか音楽とか星とか。
マイペースで更新中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
電波望遠鏡の後ろの小高い丘の上に、
鹿児島大学の光赤外線望遠鏡があります。
理学部の宇宙コースは、先ほどのVERA
観測所と連携して観測を行ってるという
ことで、ここで天文学を勉強出来る学生
はうらやましいですね~。
俺が受験した頃に宇宙コースがあれば、
迷わず目指したと思います。
天文学を勉強できる大学は非常に少なく、
レベルも高いです。
九州でこれだけの設備と一線で活躍されて
いる先生方から指導を受けられるというのは、
すばらしいことだと思います。
話しはずれてしまいましたが・・・
電波望遠鏡の横から丘に繋がる道を登って
行くと、観測所に行けます。

ちょうど、ドームのスリットが開いてる時
だったので、望遠鏡のトラス構造が覗いて
ますね~。
早速研究室を訪ねると、制御用コンピュータ
の説明を受けてから、望遠鏡と対面です。

リッチー・クレチアン式という光学系で、
西村製作所製の望遠鏡です。
パイプ構造の下の箱の中に100cmの主鏡が
入っています。写真は、ホコリを防ぐための
フタが閉まっている状態です。
ちょっと見えませんが、赤外線カメラは、
カセグレン焦点(箱の下の部分)に取り付け
て撮影します。

望遠鏡から延びているホースは、カメラを冷却
するための液体ヘリウムを供給しています。
この望遠鏡は、コンピュータ制御の経緯台です。
写真を撮るのに経緯台?って思う方もいらっしゃる
かと思いますが・・・
ちゃんと対策がしてあります。経緯台で星を追尾
すると視野回転を起こします。なので、視野回転
を補正する機構があるんですね~。
学生さんの説明で思い出しました。
実質3軸制御なんです。
写真を撮るって言えば、赤道儀しか頭になかった
ので、すぐに気づきませんでした。
考えたら、パロマ山天文台以降の大型機は、
経緯台方式が主流なんですよね。
コンピュータ制御が出来るようになってから、
複雑高価で重い赤道儀は減って来てるんですね。
西村製作所と言えば、公共天文台等の大型望遠鏡
で有名ですが、昔は小型の反射望遠鏡も作って
いたんです。子供の頃、西村製作所のカタログを
取り寄せて、15cmの反射経緯台をいつか
手に入れたいなぁと思って、ず~っとカタログ
を眺めてました。結局買えずじまいでしたが。
赤外線望遠鏡を見学した後、VERA観測室で行わ
れるミニ講演会を聴くことにしました。

難しそうな題がついてますが、解りやすく噛み
砕いて説明してもらえたので、楽しかったです。
ということで、とても楽しい一日を過ごしました。
わざわざ鹿児島まで出かけた甲斐ありです。
次は、やっぱりあそこに行かないとですね・・・
鹿児島大学の光赤外線望遠鏡があります。
理学部の宇宙コースは、先ほどのVERA
観測所と連携して観測を行ってるという
ことで、ここで天文学を勉強出来る学生
はうらやましいですね~。
俺が受験した頃に宇宙コースがあれば、
迷わず目指したと思います。
天文学を勉強できる大学は非常に少なく、
レベルも高いです。
九州でこれだけの設備と一線で活躍されて
いる先生方から指導を受けられるというのは、
すばらしいことだと思います。
話しはずれてしまいましたが・・・
電波望遠鏡の横から丘に繋がる道を登って
行くと、観測所に行けます。
ちょうど、ドームのスリットが開いてる時
だったので、望遠鏡のトラス構造が覗いて
ますね~。
早速研究室を訪ねると、制御用コンピュータ
の説明を受けてから、望遠鏡と対面です。
リッチー・クレチアン式という光学系で、
西村製作所製の望遠鏡です。
パイプ構造の下の箱の中に100cmの主鏡が
入っています。写真は、ホコリを防ぐための
フタが閉まっている状態です。
ちょっと見えませんが、赤外線カメラは、
カセグレン焦点(箱の下の部分)に取り付け
て撮影します。
望遠鏡から延びているホースは、カメラを冷却
するための液体ヘリウムを供給しています。
この望遠鏡は、コンピュータ制御の経緯台です。
写真を撮るのに経緯台?って思う方もいらっしゃる
かと思いますが・・・
ちゃんと対策がしてあります。経緯台で星を追尾
すると視野回転を起こします。なので、視野回転
を補正する機構があるんですね~。
学生さんの説明で思い出しました。
実質3軸制御なんです。
写真を撮るって言えば、赤道儀しか頭になかった
ので、すぐに気づきませんでした。
考えたら、パロマ山天文台以降の大型機は、
経緯台方式が主流なんですよね。
コンピュータ制御が出来るようになってから、
複雑高価で重い赤道儀は減って来てるんですね。
西村製作所と言えば、公共天文台等の大型望遠鏡
で有名ですが、昔は小型の反射望遠鏡も作って
いたんです。子供の頃、西村製作所のカタログを
取り寄せて、15cmの反射経緯台をいつか
手に入れたいなぁと思って、ず~っとカタログ
を眺めてました。結局買えずじまいでしたが。
赤外線望遠鏡を見学した後、VERA観測室で行わ
れるミニ講演会を聴くことにしました。
難しそうな題がついてますが、解りやすく噛み
砕いて説明してもらえたので、楽しかったです。
ということで、とても楽しい一日を過ごしました。
わざわざ鹿児島まで出かけた甲斐ありです。
次は、やっぱりあそこに行かないとですね・・・
PR
この記事にコメントする
カレンダー
カテゴリー
最新TB
カウンター
ブログ内検索
アクセス解析
フリーエリア